1. お金とは何かを知ろう
みなさん、「お金」と聞くとどんなイメージを持ちますか?おこづかい、お年玉、お店で使うものなど、いろいろな場面で登場しますよね。ここでは、小学生のみなさんにもわかりやすく、お金の役割や歴史、日本の「円」について基本的なことを説明します。
お金の役割ってなんだろう?
お金は毎日の生活に欠かせない大切なものです。では、お金にはどんな役割があるのでしょうか?下の表を見てみましょう。
| お金の役割 | 例 |
|---|---|
| ① 物やサービスと交換できる | お菓子や本を買うときに使う |
| ② 価値をはかるものさしになる | 100円のアイスと200円のジュース、どちらが高いかわかる |
| ③ ためておける(貯金できる) | 使わずに銀行や貯金箱に入れておくことができる |
このように、お金はみんなが便利に生活するためになくてはならないものです。
お金の歴史を知ろう
昔の人たちは今のお金がない時代、どのように物を手に入れていたのでしょうか?最初は「物々交換」という方法で、自分が持っているものと、ほしいものを交換していました。でも、これだと「欲しいものがもらえない」「価値がわからない」といった問題がありました。そこで生まれたのがお金です。
日本では昔、「米」や「布」、「貝殻」などが使われていました。その後、「銭(ぜに)」という硬貨が作られるようになり、さらに時代が進むと今のようなお札や硬貨になりました。
日本のお金「円」について知ろう
日本で使われているお金の単位は「円(えん)」です。1円、5円、10円、50円、100円、500円の硬貨と、1000円、5000円、10000円のお札があります。下の表で確認してみましょう。
| 種類 | 読み方 | 主な特徴・色 |
|---|---|---|
| 1円硬貨 | いちえんこうか | 銀色・とても軽いアルミ製 |
| 5円硬貨 | ごえんこうか | 真ん中に穴・黄色っぽい色・稲穂のデザインあり |
| 10円硬貨 | じゅうえんこうか | 茶色・平等院鳳凰堂の絵がある |
| 50円硬貨 | ごじゅうえんこうか | 銀色・真ん中に穴・菊の花が描かれている |
| 100円硬貨 | ひゃくえんこうか | 銀色・桜の花が描かれている |
| 500円硬貨 | ごひゃくえんこうか | 黄色っぽい色・日本一高い額面の硬貨・桐の花などが描かれている |
| 1000円札~10000円札 | – | – (詳しくは次回紹介) |
私たちの日常でよく使う「お金」ですが、それぞれに特徴や歴史があります。これからも身近なお金について少しずつ学びながら、その大切さや意味を考えてみましょう。
2. おこづかいの管理方法を学ぶ
おこづかい帳や家計簿で「見える化」しよう
小学生にお金の価値を理解させるためには、実際に自分のおこづかいを管理する体験がとても大切です。日本では「おこづかい帳」や「家計簿」を使って、お金の使い道や貯め方を記録する習慣があります。これにより、子どもたちは自分が何にいくら使ったのか、どれだけ貯まっているのかが一目で分かります。
使う・貯める・分けるの大切さを体験しよう
おこづかいは、ただ自由に使うだけでなく、「使う」「貯める」「分ける」という管理が大切です。例えば次のような表を使って、お金の流れを整理しましょう。
| 日付 | 項目 | 使った金額 | 貯めた金額 | 残り |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 | おこづかい(受け取る) | – | – | 1000円 |
| 4/3 | 文房具購入 | 200円 | – | 800円 |
| 4/10 | 貯金箱に入れる | – | 300円 | 500円 |
| 4/15 | お菓子購入 | 100円 | – | 400円 |
実際に記録してみよう!
このように、おこづかい帳に毎回記録することで、「何に使ったら残りはいくらになるか」「どれだけ貯められたか」が分かります。また、目標金額を設定して貯める楽しさも体験できます。家族で一緒に記録を確認したり、次はどう管理したいか話し合ったりすることも大切です。こうした体験から、計画的なお金の使い方や、大事な時のために貯める意識が自然と身につきます。
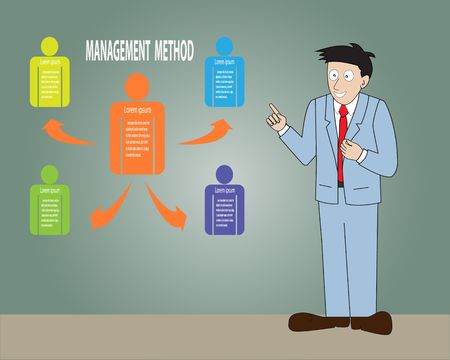
3. 買い物体験を通して価値を感じる
スーパーでのお買い物体験
小学生がお金の価値を理解するためには、実際にお金を使ってみることがとても大切です。たとえば、家族と一緒にスーパーへ行き、お小遣いの範囲内で好きなものを選んで買う経験をさせましょう。自分で商品を選び、レジでお金を支払うことで、「このお菓子は100円、このジュースは120円」と値段の違いや、限られたお金でどうやって買い物をするかを自然と学ぶことができます。
お買い物体験の流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. お金をもらう | 決められた金額(例:300円)を渡します。 |
| 2. 商品を選ぶ | 予算内でほしいものを考えて選びます。 |
| 3. レジで支払う | 実際に現金で支払い、お釣りも受け取ります。 |
| 4. 振り返り | 何が買えたか、どれだけ残ったか話し合います。 |
学校のバザーでの学び
日本の小学校では、バザーや文化祭などのイベントもよく開催されます。こうした場でも、子どもたちは自分のお小遣いから商品を購入したり、友だちと相談しながら買い物したりします。少ない予算で欲しいものをどうやって手に入れるか工夫することで、お金の使い方だけでなく、計画性や優先順位の大切さも学ぶことができます。
現金決済だからこその実感
日本では今でも現金決済が主流です。現金を使うことで「お財布からお金が減る」感覚がリアルに分かります。例えば、お札や硬貨を手に取って数えたり、お釣りをもらったりする体験は、電子マネーやキャッシュレス決済では味わえません。このような体験が、小学生にとってはとても重要です。
現金決済とキャッシュレスの違い(比較表)
| 項目 | 現金決済 | キャッシュレス決済 |
|---|---|---|
| お金の増減が見える? | ◎ はっきり分かる | △ 分かりづらい |
| 支払いの実感 | ◎ 強く感じる | △ 感じにくい |
| 管理方法 | 財布で管理する | アプリやカードで管理する |
| おすすめ年齢 | 小学生低学年~高学年向け | 中学生以降がおすすめ |
日常生活の中でコツコツ経験を重ねることが大切です。買い物体験はお金の価値や使い方だけでなく、自立心や判断力も育ててくれます。
4. 働くこととお金の関係を知る
お仕事体験や家事手伝いで学べること
小学生にとって「働くこと」と「お金を得る」関係を理解することは、金銭教育の大切な一歩です。日本では、勤勉さや協力する心が重視されており、実際の体験を通して学ぶことが推奨されています。家庭内でのお仕事体験や家事手伝いは、お金の価値や働く意味を身近に感じる良い機会となります。
家事手伝いでお小遣いをもらう例
例えば、お皿洗いや掃除など、日常生活でできる家事を手伝った時にお小遣いを渡す方法があります。これは単にお金をもらうだけではなく、「頑張って働いた分だけ報われる」という感覚を育てます。
| 家事の内容 | もらえるお小遣いの例(円) |
|---|---|
| 食器洗い | 50 |
| ゴミ出し | 30 |
| 部屋の掃除 | 100 |
| 洗濯物たたみ | 40 |
日本ならではのお仕事体験イベント
日本各地には、小学生向けの「キッザニア」や「こども店長体験」など、実際の仕事を疑似体験できる施設があります。こうした場所では、実際に働いて報酬(専用通貨)を得たり、そのお金で買い物ができたりします。このような経験は、社会の中で働く意義や、お金の流れについて自然と学べる貴重なチャンスです。
親子で話し合う時間を大切にしよう
日々のお手伝いやお仕事体験後は、「どうしてこの仕事でお金がもらえたと思う?」「どんな気持ちだった?」と親子で話し合ってみましょう。こうしたコミュニケーションが、お金の価値や働く喜びへの理解をさらに深めます。
5. ありがとうの気持ちと社会とのつながり
小学生に金銭教育を行う際には、お金の価値だけでなく、お金を使うことで生まれる「ありがとう」の気持ちや社会とのつながりについても学ぶことが大切です。商品やサービスを受けたとき、「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えることは、日本文化においてとても重要なマナーです。また、日本独自の習慣である「お年玉」も、家族や親戚との絆を深める大切なコミュニケーションの一つです。
お金を通じて学べること
| 場面 | 学べること |
|---|---|
| 買い物をする時 | 店員さんへの「ありがとう」、お金の流れ、商品の価値 |
| サービスを受ける時 | 働く人への感謝、社会で支え合う仕組み |
| お年玉をもらう時 | 目上の人への感謝、使い方を考える力 |
| 寄付や募金をする時 | 社会貢献、困っている人を助ける心 |
「ありがとう」の伝え方と社会との関わり
お金で商品やサービスを手に入れるとき、「お金を払ったから当然」と考えるのではなく、その背景には多くの人が関わっていることに気づくことが大切です。例えば、スーパーで野菜を買う時、生産者や運送業者、販売員など多くの人のおかげで商品が自分の手元に届いています。このようなつながりに感謝し、「ありがとう」と言葉で伝えることで、子どもたちは他者への思いやりや社会への貢献意識を育むことができます。
日本ならではのお年玉文化
日本ではお正月になると親戚から「お年玉」をもらう習慣があります。これは単なるプレゼントではなく、お金を大切に扱う心や、人からいただいたものへの感謝を学ぶ良い機会です。親子で一緒に「何に使いたいか」「どれくらい貯金するか」など話し合うことで、お金の使い方や計画性も自然と身につきます。
まとめ:日常生活の中でできる工夫
毎日の生活の中で「ありがとう」を言葉にしたり、お年玉やお小遣いを上手に活用する経験を通じて、小学生はお金の価値だけでなく、人とのつながりや社会全体への感謝の気持ちも身につけていくことができます。家庭でもぜひ、子どもと一緒にお金について考えたり話し合ったりする時間を作ってみましょう。


